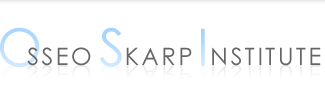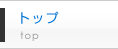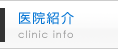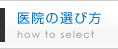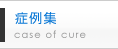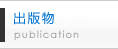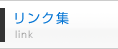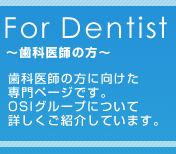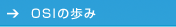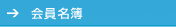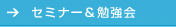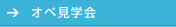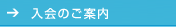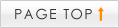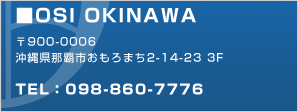トップ >> 論文抄読会
文献についての概要をお知らせ致します。
会員の皆様の日々の臨床に役立つと思われますのでご一読して頂ければ、幸いでございます。
阿佐ヶ谷北歯科クリニック院長 松川 眞敏
No.1コンタクトポイントから骨頂への距離が歯間乳頭の存在する、存在しないに与える効果
Dennis P. Tarnow, Anne W. Magner, and Paul Flecher
この研究はコンタクトエリアの基底部から骨の頂点までの距離が人の隣接面における歯間乳頭のある無しに関係していると言えるかどうかをはっきりさせるために計画された。30人の患者のトータルで288の部位が調べられた。もし、コンタクトポイントの下に空隙が見えれば、乳頭は失われたと判断され、もし組織が鼓形空隙を満たしていれば、乳頭は存在するとみなされた。結果は、コンタクトポイントから骨頂までの計測値が5mm以下の時は乳頭はほとんど100パーセント存在し、距離が6㎜になると乳頭は56パーセント存在し、距離が7mm以上になると、乳頭は27パーセント以下しか存在していなかった。
J Periodintol 1992; 63:995-996.
この研究の目的はコンタクトポイントから骨頂への距離が人間の歯間乳頭の有無に関係しているかどうかを決定することである。
- 材料と方法 -
30人の被験者の、総計で288の隣接部位、99の前歯部の隣接部、99の小臼歯部の隣接部、90の臼歯部が調査のために無作為で抽出された。すべてのコンタクトポイントは閉鎖していた、そして、計測のためにはWilliams の標準化された歯周プローブを使用した。浮腫や炎症がもし存在すれば、それを減らすためにすべての患者は測定が行われる2週から8週間前からスケーリング、ルートプレーニングを受けた。外科時に患者は局所麻酔をされ、プローブを骨頂に触れるまでコンタクトポイントの表面に垂直に挿入された。すべての測定値はミリの単位に四捨五入された。
- 結果 -
結果はテーブル1にまとめられた。コンタクトポイントの基底部から骨頂までの距離が3,4,5mmのときは乳頭はほとんど100パーセント存在していた。しかし、距離が7,8,9,10mmのときは乳頭はほとんど失われていた。
- ディスカッション -
前に外科を受けた部位での調査では、どんなはっきりとした傾向も見られなかった。 それに加えて、隣接する部位に66の部位は修復物を持っていたが、現在の乳頭の有無と、もともと乳頭があったかどうかは相関性が見られなかった。コンタクトエリアの基底部から骨頂までの垂直的な距離が決定要素であるように思えた。5mmの時は乳頭は98%も存在しているのに、たった1mm増加しただけなのに6mmになると56%の存在になり、7㎜になるとたった27%しか存在しなかったということは、とても興味深く、注意するに値する。しかし、これら3㎜の違いの中で、どうしてこんな重大な違いがあるのかという問いにたいする答えはまだ知られていない。歯間乳頭の形成における決定するための他の要素の調査、たとえば二本の歯の間の近遠心的距離とか鼓形空隙のトータルの容積とかの将来の調査が必要である。
Predictable single tooth peri-implant esthetics: five diagnostic keys
No2.単独歯インプラント周囲において予知性の高い審美性を得るための5つの診断基準
Kois JC, Compend Contin Educ Dent. 2001 Mar;22(3):199-206
周囲組織と調和の取れたインプラントの審美性を作り上げるというのは恐ろしい挑戦である。この治療の予知性というのは最終的には術者の最新手技を行う能力よりも、患者固有の解剖学的条件によって決まってしまうかもしれない。この文献では、抜歯する前にこの審美性をより正確に予測するための「5つの診断基準」(相対的な位置、歯肉の形態、バイオタイプ、歯牙の形態、骨頂の位置)について論じられている。
- 相対的な位置 -
抜歯の対象となる歯も含めた相対的な位置が重要である。なぜならこの位置関係こそが歯周組織の構造を決めているからである。理想的には隣接面の骨は約1.5mmあればインプラント修復後の吸収を最小限におさえることが出来る。
- 歯肉の形態 -
スキャロップタイプを”high”、”normal”、”flat”に分類する。乳頭歯肉と骨頂との関係は重要で、健全な歯周組織では骨頂はCEJの約2mm根尖方向にあり、スキャロップの形態に従っている。”normal“や”high”タイプにおいてはスキャロップが強い、つまり抜歯後の吸収のリスクが高いということになる。
- 歯肉のバイオタイプ -
歯肉のバイオタイプとは通常「厚い」、「薄い」で分類される。
「厚い」または「緻密な」ということは線維性であり、通常歯肉退縮に対して高い抵抗性をもつ。
- 歯牙の形態 -
「スクウェア」「トライアングル」「オベイド」、この3つの歯牙の基本的な形態はインプラント周囲の審美性に影響する。遊離歯肉より歯冠側においては「スクウェア」タイプがもっとも好ましい。
- 骨頂の位置 -
歯槽骨頂と歯肉の位置関係は、あらゆる治療介入後の歯肉レベルの予知に重要である。 “normal”、“high”、”low“に分類され、歯槽骨頂から遊離歯肉までの垂直的距離が大きいほど、退縮の危険性が高い。
- 結論 -
それぞれの5つの基準は他と密接な関係にあり、治療方針の決定を難しくしている。条件が整えば、オペをフラップレスでも行え、治療の成功率は高いであろう。さらにはどのインプラントシステムでも、外科プロトコルでも、修復のオプションを用いても同様の結果が得られるであろう(Kois JC、Kan JYK 2001)。逆に好ましくない解剖学的条件が揃えば、最新の手技をもってしても良い結果は得られないであろう。 インプラント埋入を行う前に、5つの診断基準を使うことで、もっとも高い予知性もったインプラント周囲の審美性を得ることができるであろう。“最新の手技”への過信は予知性の低い結果をもたらすだけである。
The Effect of Inter-Implant Distance on the Height of Inter-Implant Bone Crest
No3.インプラント間の距離がインプラント間の歯槽骨頂の高さに及ぼす影響*
D.P. Tarnow, S.C. Cho、S.S. Wallace J Periodontal 2000;71:546-549.
- 背景 -
インプラント周囲の生物学的幅径に関しては多数の文献が今までに発表されている。インプラントを露出させると、歯槽頂から新しく確立したインプラントとアバットメントの接合部までに、1.5~2mmの垂直性骨欠損が生じているのが見える。本研究の目的は、インプラントとアバットメントの接合部の高さにおける水平方向への骨欠損について調べ、様々な間隔のインプラント間で生じる骨頂の高さに、この水平方向への骨欠損が及ぼす影響の有無を判定することであった。
- 方法 -
研究方法として、2本のインプラントが隣接して埋入されている36名の患者のX線写真を撮影して測定した。骨頂からインプラント体の表面までに及ぶ水平性骨欠損を測定した。さらに、隣接するインプラントの先端を線で結び垂直性骨欠損も測定した。インプラントショルダーで測定したインプラント間の距離に関するデータを基に、患者を2群に分けた。
- 結果 -
隣接するインプラント間で生じた水平性骨欠損は、近心側ではインプラントショルダーから1.34mmで、遠心側ではインプラントショルダーから1.40mmあることが明らかになった。さらに、インプラント間の距離が3mm以上の場合は、垂直性骨欠損は0.45mmで、3mm未満の場合は1.04mmであった。
- 結論 -
一般に言われている垂直性の要因に加えて、インプラント周囲の骨欠損が生じるには水平性骨欠損も一因であることが本研究で明らかになった。この現象の臨床的意義は、垂直性骨欠損が進行することによって、隣接歯の歯冠のコンタクトポイントの底部から歯槽骨頂までが大きくなることである。この大きさによって、以前に2本の歯の間に存在した歯間乳頭が、インプラント埋入後もその間に同様に存在するか否かが決まることになる。審美領域に複数のインプラントを埋入するときは、インプラントとアバットメントの接合部の直径が小さいインプラントを使用する方が有益と考えられるが、インプラントとアバットメント接合部の高さでインプラント間の距離が最低3mmあれば骨は維持できる。また、太いインプラントではインプラント間の距離が取れず、歯槽骨の吸収増大を誘発する可能性があるため、審美領域で並べて埋入することは勧められない。隣接するインプラント間の歯槽骨吸収によって歯間乳頭が影響を受ける可能性に関する研究は現在進められている。
- コメント -
この研究の意義は、一般に水平性骨欠損が片側1.3~1.4㎜生じるため、インプラント間の骨頂の垂直性骨吸収を少なくし歯間乳頭を維持するためには、インプラント間の距離が最低3㎜以上必要であり、審美領域には4㎜以下のインプラントを使用すべきであると言うことを示唆している。2000年の論文であり、高い評価に値する。アストラインプラント(タイオブラスト、マイクロスレッド、コニカルシールデザイン、コネクティブカントゥアー)の場合も同じように考えてよいのか?
OSI STUDY CLUB LITERATURE SEMINAR ASSIGNMENT
STAFF: Dr. Seiichiro Kinjo
DATE: Saturday,March 15th, 2008
TIME: 13:00 - 18:00
AT: DENICS INTERNATIONAL
Articles below are from Dr. Tarnow, Dr Kois and Dr Salama
1 Dr Tagahara Akihiro
Tarnow DP, Magner AW, Fletcher P. The effect of distance from the contact point to the crest of bone on the presence or absence of the interproximal dental papilla. J Periodontol 1992;63:995-996.
2 Dr Yosihiro Okamoto
Kois JC. Predictable single tooth peri-implant esthetics: Five diagnostic keys. Compend Contin Educ Dent 2001;22:199-208.
3 Dr Kannji Kouno
Tarnow DP, Cho SC, Wallace SS. The effect of inter-implant distance on the height of inter-implant bone crest. J Periodontal 2000; 71: 546-549.
4 Dr Daiti Yonezawa
Salama H. Salama MA. Garber D. Adar P. The interproximal height of bone: a guidepost to predictable aesthetic strategies and soft tissue contours in anterior tooth replacement. Pract Periodontics Aesthet Dent 1998 ; 10(9) : 1131-1141.